
なぜか人が離れていく理由7選|いくつ当てはまりますか?
なぜか人が集まってくる人がいる一方で、なぜか人が離れていく人。人が寄ってこない、友達ができない、飲み仲間ができない。そんな経験を持っている人は結構多い気がします。イベントや飲み会を企画しようにも、参加者が誰もいない。飯食いに行きましょうよ~、とか奢ってくださいよ~、とか言う後輩がいない。
解放デビュー。今日は残りの人生のデビュー当日。ずっと笑ってなかった生活から解放され、スッキリした気持ちで残りの人生をスタートしたい。

なぜか人が集まってくる人がいる一方で、なぜか人が離れていく人。人が寄ってこない、友達ができない、飲み仲間ができない。そんな経験を持っている人は結構多い気がします。イベントや飲み会を企画しようにも、参加者が誰もいない。飯食いに行きましょうよ~、とか奢ってくださいよ~、とか言う後輩がいない。

理系の研究室の学生は、かなりうつ病になりやすいと思います。僕も学生時代は工学部でしたが、大学4年時に研究室に配属された後は、あまりにしんどくてうつ病になりそうでした。人間関係が超閉鎖的で拘束時間が長くて、もはや犯罪者以下の扱いです。今回大学の研究機関の闇の部分について書きます。

ここに人間関係の罠があるような気がします。というのも仲の良いパターンというのは、結構以下の2つに大別されるような気がするからです。(1)居心地がいい関係(2)お互い高め合う関係だいたい想像付くように、前者の居心地がいい関係というのが、かなりまずい関係です。今回は、この2つの仲の良い関係について、思うところを書いていきたいと思います。

この職場の人と話が合わないという問題は根が深いような気がします。馬が合わない、肌が合わない、価値観が全然違う……、たぶんこんな感じの表現になるのかなと思います。人と話が合わないということは、その人の根底にある考え方や哲学に大きなギャップが生まれている状況です。自分の求めている人間関係とはかなりギャップがある状態。

本当に誰に対しても受け止めないといけないのでしょうか?自分を否定したり、批判ばかりしている者、自分に対して毎日ガミガミ言う人、とてもじゃないけど、この人と付き合っていても成功できそうにない人、どう考えても付き合っていて得られるものがなさそうな人に対しても、万遍なく付き合っていなくてはならないのでしょうか?

「人に興味を持たれない」という悩みを耳にすることがあります。自分もよくこういう悩みに囚われたことがあります。悩みというより、「人気者になりたい」「注目されたい」という感じでしょうか。これを恋愛に限定すれば「もっとモテたい」「女の子から面白いと思われたい」という気持ち。20代は本当にそういう気持ちが強かったんですが、

どう接したら良いかわからなかったり、話が合わなかったり、やたらと厳しい先輩がいたり……。新たな人間関係、特に学校や職場内で循環する人間関係というのは、自分が選択できるわけではないので、ストレスもかなり大きくなると思います。社会というのは閉鎖的な空間を意味するとつくづく実感しますwww

車を例にするのであれば、ハンドルを動かす運転手が願望(上質世界)、エンジンが5つの基本的欲求とされています。運転手がハンドルを切ると、多くの車では前輪が動かされ、後輪はまったく角度を変えないと思います。これが行動のメカニズムのミソな部分で、

基本的に人間は自分と未来は変えられる、過去と他人は変えられないと言われます。奥さんの場合は「夫が自分に振り向いてくれない」「どうやって趣味の時間を自分たちに向けさせるか」ということばかり考えてしまっています。旦那さんの立場になると、自分の上質世界を剥がされようとしているのですから、気持ちの良いはずがありません。

人と違うのは当たり前であって、決して「間違い」ではない。でも、中には自分との「違い」を「間違い」としてしまう残念な人もいます。人と違うことは異常なのではなく、むしろ魅力的なのです。同調圧力が異常なほど強い日本人は、まずそのことに気付くべきだと思います。

始めに断っておくと、この記事はfacebookの友達削除してもばれない方法を書いた記事ではありません。友達を削除しても別に相手に通知が行くわけではないですが、これが案外ばれるんです。友達が100人程度と、あまり多くない人を削除すれば誰に削除されたかすぐわかるでしょうし、

少し職場で疲れ気味だ、人間関係で良くないことが最近続いている、そういう人は人間関係の断捨離について考える時期に来ていると思います。自分は自由の欲求がとても高い人間で、束縛されることがかなり苦手なので、人間関係に関するストレスには敏感かもしれません。では、どういう人を断捨離していけばいいか、いろいろ考えてみたい

選択理論心理学では、このような願望のイメージ写真がたくさん貼られている場所(アルバムのようなものと言えば良いと思います)を上質世界といっています。ようは自分の願望が格納されている場所と捉えれば良いと思いますが、厳密に言うならば、5つの基本的欲求を1つ以上満たすイメージ写真の格納場所と言うことで良いと思います。

そういう人達に1回ガミガミ怒られたり、責められたりすると、落ち込んでしまい、自己嫌悪に陥ってしまいます。これが後で復活すれば良いのですが、これを引きずって、また失敗して怒られる。このサイクルを繰り返すと、今度は他人が嫌いになり、嫌いな場所だけを探してしまいがちです。そうなってくるともう悪循環です。

選択理論心理学的に言えば、これから話す5つの基本的欲求を満たすのが上質世界ということになります。5つの基本的欲求とは、自分達の行動を駆り立てる、生まれながらにして持っている欲求のことです。欲求を満たせば気分が良いし、満たせなければイライラしたり落ち込んだりします

それでもビジネスや家庭の場で、大人達がこの人間関係を破壊する習慣を日常の場で使ってしまう。こう考えると人間はある意味で、自分を含めて頭の悪い生き物だと感じる時がありますが、これは以下の外的コントロールの考え方があるからだと言われています。

あらゆる人間関係において重要な習慣についてシェアしたいと思います。生きている間は、ずっとこの習慣を使い続けることが自分の目標の1つです。なんといっても人間の悩みの85%は「人間関係」なのですから、それを良好にする習慣があれば、それを身に付けるに良いことはないです。
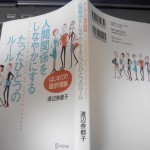
それでは、他にわかりやすく選択理論について書かれた本はどれか、と言われると、「人間関係をしなやかにするたったひとつのルール」(渡辺奈都子著、Discover21刊)という本です。ちょうど著者の渡辺奈都子先生の講演があったので聞きに行ったのが、この本を読むきっかけです。

この選択理論心理学を学んでいる人達といろいろ話してみて、「あれ、何でこんなにみんな明るくて楽しそうなんだ?」という感覚を覚えたのです。それ以降、なんとなく興味を持って、選択理論の勉強会に時折参加するようになりました。まだ漠然とですが、何であの時みんな楽しそうなのかも少しずつわかってきたような気もします。