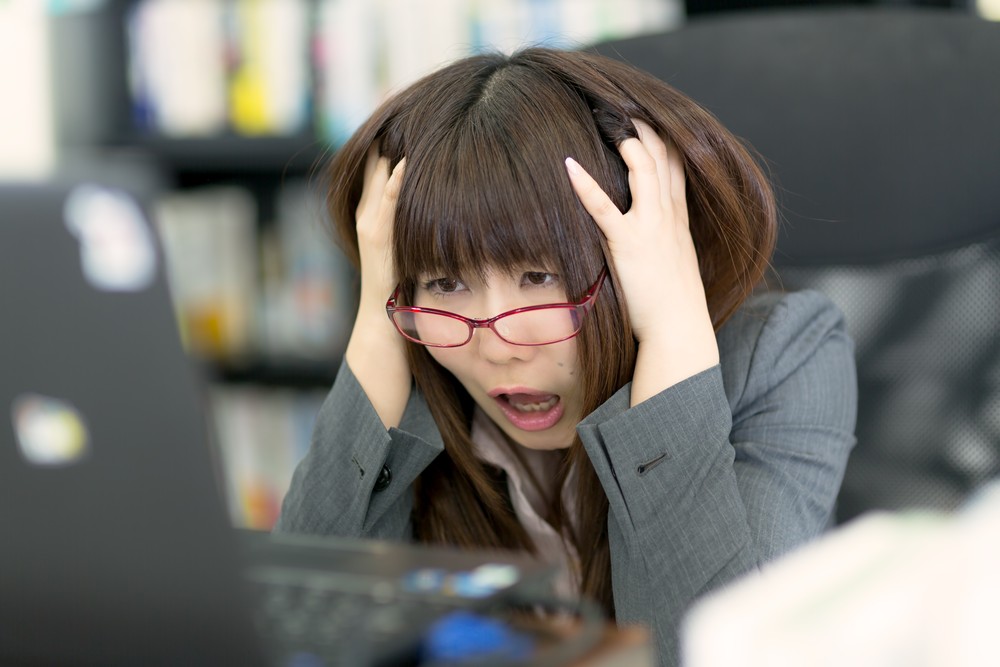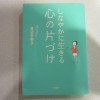確定申告をする必要のあるサラリーマンは、年収2,000万円以上を超えた場合、年間20万円以上の副収入があった場合、投資での運用益が確定した場合等に限定されているため、サラリーマンで確定申告をしている人はかなり少ないのではないかと思います。
会社の給料以外に副業をしていない、投資もしていないという時点で個人的には恐ろしいことだと思っていますが、さらにこの状況では税金に関する知識も身につかないということになります。
源泉徴収制度の恐ろしいところは、まさにこの部分で、勝手に税金を処理してくれるということは、サラリーマンに考えさせる機会を奪っているということになります。
個人事業主の人が確定申告の時期にバタバタするのを見て、「自営業の人は大変だな~」なんて思っている人も多いと思いますが、
本当はサラリーマンでも最低限の税金の知識は身につけないと損してしまいます。家を買った人や生命保険に入っている人、株やFXに投資している人、不動産投資をしている人であれば意識していると思いますが、
その他に医療費控除や寄付金控除や、今回話す特定支出控除についても知っておく必要があります。
また、それだけではなく、副業の年収が20万円以下でも、赤字で申告できるのであれば、確定申告をしておいた方が節税になります。
このように、サラリーマンでも知っておいた方がいい税金の知識は結構あります。
今回は、2013年度の改正から意外と知っておいた方が役に立つのではないかと思われる、特定支出控除について書きたいと思います。
この記事の内容
■特定支出控除の対象
特定支出控除とは、業務に必要な費用だったのに会社経費で落とすことができず、自腹で支払った場合に、給与所得控除からさらに積み重ねて還付できる制度です。
特定支出の対象を具体的に書くと、以下のような感じです(国税庁HPより引用)。
1. 一般の通勤者として通常必要であると認められる通勤のための支出(通勤費)
2. 転勤に伴う転居のために通常必要であると認められる支出(転居費)
3. 職務に直接必要な技術や知識を得ることを目的として研修を受けるための支出(研修費)
4. 職務に直接必要な資格を取得するための支出(資格取得費)
※平成25年分以後は、弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費も特定支出の対象となります。
5. 単身赴任などの場合で、その者の勤務地又は居所と自宅の間の旅行のために通常必要な支出(帰宅旅費)
6. 次に掲げる支出(その支出の額の合計額が65万円を超える場合には、65万円までの支出に限ります。)で、その支出がその者の職務の遂行に直接必要なものとして給与等の支払者より証明がされたもの (勤務必要経費) (1) 書籍、定期刊行物その他の図書で職務に関連するものを購入するための費用(図書費)
(2) 制服、事務服、作業服その他の勤務場所において着用することが必要とされる衣服を購入するための費用(衣服費)
(3) 交際費、接待費その他の費用で、給与等の支払者の得意先、仕入先その他職務上関係のある者に対する接待、供応、贈答その他これらに類する行為のための支出(交際費等)
※6の支出については、平成25年分以後、特定支出の対象となります。
これを見ると、人によっては、いろいろ思いつくところが出てくると思います。
「あれ?あの取引先と飲みに行ったお金とか自腹で払ったな」→上記6.
「そういえば今年スーツ買い換えたぞ」→これも6.
「私派遣社員だから交通費自腹なんだよね~」→上記1.
「あの資格の試験料は自腹で払ったぞ」→上記4.
「資格の受験費は経費だったけど、テキストは自腹だ」→上記6.
「あのセミナーは自腹だ。上司が勧めたから行ったのに経費落ちなかった」→上記3.
■特定支出控除の仕組み
この特定支出控除ですが、このような範囲になったのは2014年になってからで、それまでは上記6.の範囲は含まれていませんでした。つまり交際費や資格の勉強代なんかは対象外でした。
また、改正前は合計額が給与所得控除額を上回ることが要件だったので、特定支出控除は、存在していただけで、ほぼ形骸化していました。
しかし、この要件も、2013年から給与所得控除の1/2に緩和されており、また適用範囲も拡大したことで、ようやく日の目を見る控除になってきた。そんな感じです。
2015年現在の特定支出控除の仕組みであれば、年収500万円の会社員の適用額は77万円(改正前は154万円と、かなりハードルが高かった)。
つまり、特定支出が100万円の場合は23万円を控除できる計算になります。
自分の場合、今の仕組みでもかなりハードルが高いですが、人によっては知っておくと得する制度です。なかには知らないと損する人もいるかもしれません。
ただ、適用範囲が拡大したといえ、会社から証明書が必要になるので、そこは注意です。